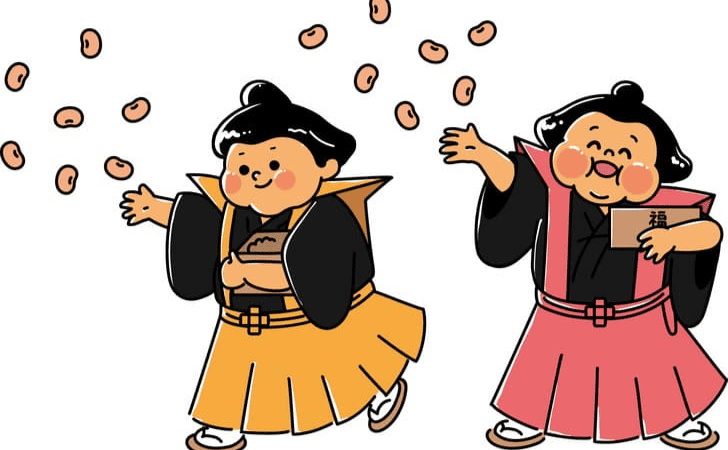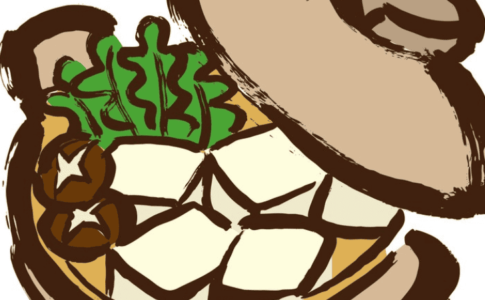2025年の節分は2月2日。
節分は立春の前日にあたる日で、季節の変わり目をあらわす行事です。節分の由来は、古代中国の「立春」の行事に由来しているとされています。
立春は、春の始まりを祝う行事で、邪気を払い、幸運を呼び込むために、いろいろな行事が行われました。
節分の最も有名な行事は、鬼を払い、福を招くための「鬼は外、福は内!」という掛け声と、豆まきです。
恵方巻を食べるのはもう定着してますね。スーパーやコンビニでも色々な恵方巻が並び、見るからに美味しそうで食べたくなってしまいますね。
節分に恵方巻を食べるのはいつから始まったの?
昔から恵方巻を食べていたのかと言うとそうではなく、恵方巻を食べ出したのは1970年代頃。
大阪の海苔や寿司の組合が恵方に向かって寿司を無言で丸かぶりすると幸せになると言うチラシを配布して販促したとか。
それ以後、スーパーや百貨店、小売店、が参入して2000年代に入ってくるとコンビニが積極的に販売活動をするようになって現在に至っているそうです。
鰯を食べて1年間の平穏と無事を祈る
祖父から聞いた話によると、鰯の頭を葉付きの柊の枝に挿して玄関先に飾って鬼が家の中へ入ってくるのを防いで1年間の平穏と無事を祈願したそうです。
何を食べたのかと言うと、「鰯」です。節分に鰯を食べるのが風習でした。

出典:https://prtimes.jp/
それにしても玄関に鰯の頭を飾るとは、今の時代には到底想像もつかないですね。
柊のトゲと鰯の臭い匂いで邪気を払ったと言うことです。
そう言えば、祖父が存命の時玄関に鰯を飾ってあるのを見た記憶があります。
豆まきの由来
豆まきと言うと「鬼は外、福は内」と言いながら豆をまいているのを思い浮かべます。
年男(一家の主人)が窓や戸を開けて豆を息よく投げるようにまき、終わると鬼が入ってこないように窓や戸を閉めて豆を拾い自分の歳の数だけ食べるとその年の間、病気にならず健康でいられる言う風習があります。
豆まきは、中国の古代から伝わったもので、年の初めや季節の変わり目に宮中行事の追儺(ついな)が始まりと言われています。
この儀式は、悪霊や災厄を払う儀式で、豆が使われていたそうです。
日本での豆まきは平安時代と言われています。当時の宮中で中国と同じように立春の前日にあたる「大晦日」に「追儺式(ついなしき)」という儀式が行われていました。
豆も使われていたので現在の豆まきの原型だとなっていると言われています。
今や、家庭、学校や保育園、商業施設や神社でのイベントとなって来ました。
商業施設や神社のイベントでは有名人が豆をまいて、一般の人々も参加して豆を受け取り楽しむことができますよね。
豆まきの意味
節分の豆まきには、季節の変わり目に起こりやすい病気や災害などの邪気を追い払い、福を招くという意味が込められています。
なぜ炒った豆を巻くのかと言うと、拾い忘れた豆から芽が出るとよくない事が起きると言われているから炒った豆を使う、また、「魔目(鬼の目)を射る=炒る」という語呂合わせにかけています。
まとめ
節分に恵方巻を食べるのはいつから始まったのか、豆まきの由来や意味を解説しました。
節分の豆まきには、病気や災害などの邪気を追い払い、福を呼び込むという意味が込められていたのですね。
子供の時は何も考えないで節分の意味も由来も知らず、ただ、恵方巻を食べて豆まきを楽しんでいました。
こういう伝統的な行事が子供達にもわかりやすく伝えていけると良いですね。